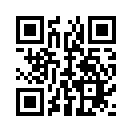from 校長室
第20回卒業証書授与式を終えて
長く居座った10年に一度といわれる大寒波が東に抜け、待ちに待った春の暖かな日差しが振りそそぐ3月1日(土)、140名の卒業生が学び舎を巣立っていきました。土曜日の卒業式とあり、たくさんのご来賓と保護者の皆さん総勢800名を超える多くの方々に参列いただきました。厳粛な中にも暖かさのある素晴らしい式となりました。ありがとうございました
卒業した3年生が入学した令和4年4月は、新型コロナウイルス感染症による重傷者が減少するも、変異株が次々と発生し、第6波、第7波と波が大きくなり、収束のきざしも感じられない時期でした。ソーシャルディスタンスとマスクが欠かせない厳しい条件下での高校生活スタート、中学時から引き続き学校行事や部活動が制限され、友達とじっくり話し合う機会もなく、窮屈で充実感に欠ける生活だったと思います。自分を表現できず、思い悩んだことも多くあったことでしょう。幸いにして昨年度早々に、5類に移行し、この2年間はまさに学校の中心として学校行事や部活動を牽引してくれました。応援練習、対古川高校定期戦、築高祭、体育祭、地域のお祭り等のボランティア活動など、皆さんは昨年卒業した先輩たちとともに 協力して新たなスタイルを模索し、3年生になった今年度は、新たな伝統として後輩に模範を示してくれました。様々な個性を持つ仲間と、互いに認め合い、助け合い、そして学び合い、たくましく成長しました。我々教職員もそのような献身的な姿や思い悩む皆さんと向き合うことから、よりよい教育の在り方について思いを巡らせ、考えを深めることができたと思っています。感謝いたします。
前生徒会長の答辞では、学校生活で、さまざまな失敗やトラブルを経験し、計画を立てたり問題解決したりする力の大切さに気づくことができ、そこから大きく成長できたことや不安定な心理状態の自分に向き合ってくれた両親や先生方への感謝の思いをしっかり語ってくれました。また、式の最後の校歌斉唱では、3年生が大粒の涙を流しながら母校への感謝も思いを胸に力一杯声を張り歌っていました。また、後輩たちも先輩への感謝とその門出を祝うべくいつも以上にしっかり歌ってくれました。築高生の思いが詰まった歌声に感動し、私も感極まってしまいました。
過去は現在や未来の土台となります。幸せな思い出は将来幸せになれる根拠となり、つらい思い出はそれを乗り越えた証拠となっています。この卒業を機会に今まで過ごしてきた18年間をしっかり振り返り土台をしっかり見定めてもらいたいです。
「年年歳歳花相似たり、歳歳年年人同じからず」という詩がありますが、花も人も変化し続けています。確かに「変化」は、先が見通せず不安な気持ちになります。しかし、「変化」するからこそ、その先には必ず希望が見えてきます。特に高校生はこれから間違いなく大きく変化、成長していきます。希望の塊なのです。
卒業という節目は、「これまで培った土台は何か」「何を卒業し、何をはじめるか」など、自分の来し方と行く末を探究する機会となります。人生の節目の過ごし方を学ぶまたとない好機です。竹は節があるから高く成長することができます。我々人間も同じです。節目、節目を大切にし、人生を豊かなものにしてもらいたいです。
ともに 未来のくりはらを 創ろう
先月の29日(水)に一迫商業高校の栗原版デュアルシステム学習報告会がありました。「デュアルシステム」とは学術的教育と職業教育を同時に進めるシステムです。一迫商業が取り組んでいる「栗原版」は学校での理論的な学習と栗原市内の企業での実習を並行して実施し、実践力を高めていく学習システムです。市内40あまりのたくさんの企業に協力してもらっています。少子高齢化が進む栗原地域、その流れを変え、発展させてくれることを大きく期待されており、その期待にしっかり応える学びを展開していました。
まずは2年生、「総合的な探究の時間」で職業研究を進めるほか「社会人としてのマナー」を学び、3日間市内の企業での実習に臨みました。経験を通しての感想と自分の課題、今後の学習の目標をそれぞれが堂々と話してくれました。社員と一緒に過ごし、働くことの大変さと責任、そして楽しさを自分の言葉で語ってくれました。
そして3年生、商業科目「総合実践」の学習の成果の発表でした。企業実習班・販売実習班・起業家研究班の3つに分かれ各20分あまり時間をいっぱいに使い熱のこもった発表でした。企業実習では週に2回3時間程度、実際に社員と一緒に働き、自分なりに身につけた職業観や勤労観を自信を持って発表してくれました。介護現場での感動的な体験がきっかけでさらに学びを深め、看護の世界に進む決意をしたことなど具体的に語っていました。販売実習班ではマーケティングをし、実際に商品を仕入れ販売して利益計算を行う等販売店さながらの活動をパフォーマンス挟みながら元気よく発表してくれました。はじめはうまくいかず苦労したようでしたが、販売体験を重ねながらそれぞれがノウハウを身につけ、充実した笑顔は印象的でした。販売の売り上げを栗原市に寄付するなど地域への社会貢献も果たし、自信に満ちあふれた立派な発表でした。起業家研究班は、ITを駆使した先進的な取り組みを行っていました。地域の活性化を図るべく観光戦略をあれこれと考え、トライアンドエラーを重ねながらも立派な成果物を残しました。「きてみらいんくりはら市」と題した観光デジタルマップは素晴らしい出来、一度手に取って見たもらいたいと思います。また、さらに栗原市のふるさと納税アップを目標に返礼品開発を進めていました。地域の食品点と研究を重ね、完成までには至りませんでしたがその続きを後輩に委ねる姿は感動的でした。
我が築高も「日本一住みやすい街くりはらプロジェクト」を2学年中心に「総合的な探究の時間」で進めています。地域をフィールドに、地域を元気にするため地域の課題を発見しその解決策を考えています。これに対し、一迫商業の取り組みは実体験があり、そして深くて重みがあり非常に刺激になります。
来年度の入学生から一迫商業は築館高校のキャンパスとなります。今以上に近しくなります。お互い切磋琢磨し、ともに「未来のくりはら」を創り上げましょう。
築高21年目「進化」の年に
新年あけましておめでとうございます。今年は曜日の関係で年末から奇跡の9連休、日本海側は記録的な大雪となっていますが、太平洋側は荒れることなく非常に穏やかな年末年始を迎えることができております。
今年は昭和100年、戦後80年の節目を迎えます。終戦以来、日本は人々のたゆみない努力により、今日の平和と繁栄が築き上げられてきました。一方、ロシアのウクライナ侵攻や中東イスラエルでの紛争など世界各地で多くの命と財産が失われ、深い悲しみを覚えます。私を含め今や太平洋戦争を知らない世代が大勢を占めています。先日、日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞しました。この節目に気持ちを新たにし、平和な世界を築づいていくために、人々がお互いの違いを認め合いともに手を携えて力を合わせて行かねばと思っています。
さて、今年の干支は乙巳(きのとみ)となります。「木」と「火」のエネルギーが合わさった特別な意味を持ちます。「乙」は成長の兆しを表す若木を象徴し、「巳」は発展を象徴する「火」の気を持ちます。これらが重なることで新しい方向に進むための準備や新たな始まりに適した年になるとされています。特に巳年は蛇が脱皮して生まれ変わるように再出発のよいタイミングを暗示しています。脱皮による再生を象徴とする巳年は、古代から「生命力」や「復活」のシンボルとされてきました。2025年もこの特徴を受け継ぎ変化を受け入れることで成長できる年になりそうです。現状を打破し、未来への展望を広げるために必要な「進化」のテーマが強く意識される年になりそうです。
築館高校は今年創立から21年目を迎えます。旧築館高校と旧築館女子高校が統合して20年が経過しました。「3年後、なりたい自分がそこにいる」のキャチフレーズのもと文武両道に加え、人のため精神を培い、社会に有為な人材を多数輩出してきました。少子高齢化が進む栗原市ですが、これからも築館高校は栗原のど真ん中で地域の皆さんに元気と勇気を与え続けていきます。今年の4月から一迫商業高校が本校のキャンパス校となり、新たなステージに向かいます。校舎東側の休耕田に第2グランドが造成され、その工事がスタートしています。
また、賞状の贈呈式やインタビューなど築高生の活躍を讃える一つのアイテムとして市松模様にデザインされたバックをPTAから寄贈していただきました。ありがとうございました。このバックを背に多くの築高生が称賛される機会が生まれればと思っています。次なる10年に向かい「進化」する年となります。築高生の活躍をご期待ください。
SNSを有効に利用するために
ここ数年SNSは世論を動かすほどの影響力を持ち、特に今年は選挙戦にSNSが利用され、その効果の大きさが話題となりました。今や日本のソーシャルメディア利用者数は、2023年で1億580万人といわれ、若者中心のコミュニケーション手段からあらゆる年代におけるコミュニケーション手段へと変化しています。そう考えるとその絶大な影響力は当然のことと納得させられてしまいます。
SNSのメリットは、まずリアルタイムで情報を得られることです。ニュースやトレンドが瞬時に拡散されるため、常に新しい情報を追うことができます。SNSを使うことで、社会的な出来事や興味のある分野の最新情報をすぐに知ることができます。また、友人や家族と簡単にオンライン上で繋がることができる手段としても非常に有効です。特に忙しい現代社会では、直接会う機会が減りがちですが、SNSを通じて日常の出来事や感じたことについてシェアすることで、関係を深めることができます。写真やメッセージを通じてお互いの生活を知り合うことができるため、コミュニケーションをより多く取ることができるメリットがあります。さらに、誰でも気軽に情報を発信できるのが特徴です。個人の意見やアイデアを投稿することで、自分の声を広めることが可能です。投稿がシェア・拡散されることで、多くの人々とつながるチャンスも増えます。この特性から、SNSには多くの人に支持されるインフルエンサーと呼ばれる人たちもいます。
SNSは新しい人との出会いを促進するプラットフォームでもあります。共通の趣味や興味関心を持つ人たちと簡単に繋がることができ、情報交換もできます。SNSを通じてオンラインイベントやグループに参加することで、世界中の人たちと繋がることができます。日々の実生活で閉塞感があっても、SNSで世界中の人たちとつながり救われることもたくさんあります。
一方で、気軽に情報発信できる分、個人的な情報が流出するリスクも高まります。プライバシー設定が不十分だと、知らない人から自分の個人情報にアクセスされる可能性があります。また、悪意のある第三者によるアカウント乗っ取りや詐欺の被害に遭うこともあるため、投稿する内容やプライバシー設定には注意が必要です。また、誹謗中傷やネットいじめといった人間関係のトラブルを引き起こすことがあります。特に匿名性が高いため、攻撃的な言動が助長されやすく、投稿が拡散されることにより被害を受ける人も出てきます。健全なやりとりを促すために、ユーザー間での意識を高め、誹謗中傷への厳しい対策が取られることが求められています。
リアルタイムで情報を入手できるというメリットがあるSNSですが、裏を返せば信憑性の低い情報やフェイクニュースが溢れやすいという特徴もあります。情報の真偽を確認せずにシェアしてしまうと、自分自身が誤った情報の拡散者になりかねません。常に情報源をしっかり確認し、フェイクニュースの可能性を疑うことが重要です。また、重大な事件や話題に関しては、事実を知らずに反応することが多いため、注意が必要です。「闇バイト」情報などは最たるもの、うかつに乗らないように!!
先日、オーストラリアの議会が16歳未満のSNSの利用を禁止する法案を可決しました。1年後に施行される見通しです。暴力や自殺、いじめなど「有害な投稿」から子供を守るのが目的で、対策を講じなかった運営企業に罰金を科す等です。年齢認証など課題も多いですが、未成年が犯罪に巻き込まれるなどSNS対策が世界的課題となる中、オーストラリアの踏み込んだ対応は海外に波及する可能性があります。
コロナ禍の影響もあったと思うのですが、SNSやインターネットへの書き込みは単語やスタンプ(イラスト)によるやりとりで感情的なものが多く、社会問題になるほどに誹謗中傷の内容が多くなっています。社会も感情に流され 正しい理論が受け入れられない、そんな混沌とした世の中になっています。オーストラリアの対応もわからないわけではありません。
これからSNSの利用者が増えるに従い、ますます問題も増えていきます。一つの情報を鵜呑みにするのではなく、丁寧に調査する必要があります。発信する場合も感情的になって周囲に迎合してすぐ反応してはいけません。根拠をしっかり抑え、論理的にそして説得力あるわかりやすい言葉で自己の考えをしっかり表現しなければ、思わぬ炎上を生んでしまいます。この世の中を正す上でも重要と思います。スピードが重視される社会ですが、築高生にはじっくり問題に向き合い前向きな理論を展開し、社会に貢献してくれることを期待します。
読書をとおして「ホンモノ」になろう
10月26日(土)から11月24日(日)まで「秋の読書推進月間」が開催されています。全国学校図書館協議会の調査によると、読書は「大切だと思う」「どちらかと言えば大切だと思う」と答えた割合は小中高ともに約9割に上ったが、1ヶ月に1冊も本を読まなかった児童生徒の割合(不読率)は高くなっています。特に高校生は48.3%。2人に1人は1冊も読んでいないようです。
築高は、毎朝BUT(ブラッシュアップタイム)の10分間、全校生徒で朝読書を行っています。毎朝皆さんの朝読書の様子を見ておりますが、思い思いの本を持ち寄り真剣に読んでいるようです。築高生はたぶん「読書は大切だ」と思っている人はほとんどでしょう。是非自分なりの目的を持って取り組んでほしいと思っています。
さて「読書」には下記のように15もの効用があると考えられます。
| ①語彙力が養われる ②仕事に必要な教養が身につく ③新しい価値観を知ることができる ④ひき出しが増えるため、コミュニケーションが上手くなる ⑤文章を書くことが上手くなる ⑥論理的な思考が身につく ⑦記憶力が向上する ⑧何事にも集中して取り組めるようになる ⑨気分をリフレッシュし、ストレス発散になる ⑩どこでもできるので、移動時間などの無駄な時間が減る ⑪成功者や偉人の考え方を参考にできる ⑫趣味にすれば、お金があまりかからない ⑬本質を見極めるのが早くなる ⑭本を読んでいるという事が、自信になる ⑮本を読む人の方が収入が高いというデータがある |
3年生になると進路実現に向けて様々な文章を書く機会が増え、今の時期、大変苦労しています。文章力は生きている上で必ずといっていいほど必要になる能力です。社会人になってからも仕事のプレゼン資料や業務連絡のメールの作成など様々な場面で文章力が必要です。文章力は書くことでも鍛えられますが、読書でたくさんの文章を目にすることでも効果的に鍛えられます。自分が知らなかった言葉や表現に数多く触れられるため、たくさん本を読んで様々な文章に触れることで文章が書くことが上手くなります。
また、読み手に自分の考えを伝えるには、相手に伝わるような文章構成が必要です。一冊の本の中には著者による論理的な文章がたくさん詰まっています。読書によって著者の考えた文章を読み解いて理解することで、著者による論理的な思考力を学べます。様々な著者の本を読むことで、その都度論理的な思考が身につくことにもつながります。「書く」ということを意識して読んでみてください。
人間は自分の価値観で普段は生活しています。しかし、それだけでは考え方が偏ってしまったり、新しいアイデアが浮かばなくなってしまいます。人によって価値観は様々ですが、読書によって本の数だけ自分にはない新しい価値観を知ることができるのです。新しい発想力や考え方が偏らないためにも、さまざまなジャンルの本を読み、新しい価値観に出会い自分を成長させてほしいです。
また、本は文章からの情報を読み解いて内容を理解しなければなりません。読書すると読解力や洞察力、理解力が高まるため、本質を見抜くのが上手になります。本質を見極めるということは、物事について本当に大切な部分が理解できているかどうかということ。
読書によって本質を見極めるのが早くなれば、仕事をスムーズに進めやすくなったり、人とのコミュニケーションも上手くいきやすくなります。
ぜひ、築高生には物事の価値観を広げ、本質を見抜く力もつけてもらい「ホンモノ」の人材になってほしいと思っています。